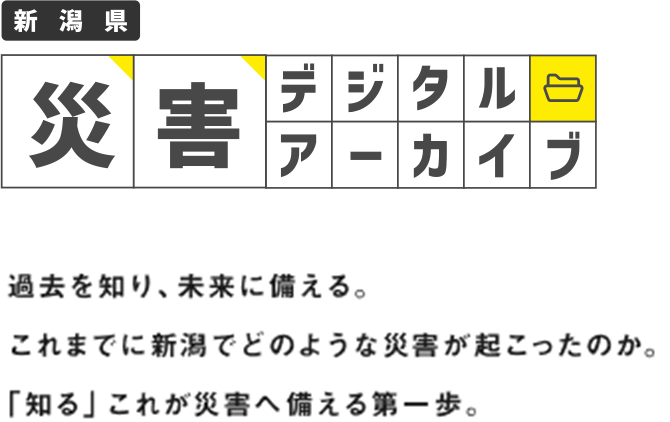本文
新潟県中越大震災

2004年10月23日


妙見の大崩落/写真提供:長岡市
災害と被害の概要
| 災害発生時刻 | 2004年(平成16年)10月23日午後5時56分 | 最大震度 | 7 |
|---|---|---|---|
| マグニチュード | 6.8 | 最大震度発生地域 | 川口町(現長岡市) |
| 震央 |
新潟県中越地方 北緯 37度17.5分 東経 138度52.0分 |
震源の深さ | 13km |
| 人的被害(県内) |
死者:68人 重軽傷者:4,795人 |
建物被害(県内) |
【住家被害】 全壊:3,175棟 半壊:13,810棟 一部損壊:104,619棟 |
2004(平成16)年10月23日午後5時56分、新潟県中越地方を震源とするマグニチュード6.8の地震が発生。震度計による観測が始まった1996年4月以降、初めて最大震度7を観測した。震源の深さは13km。川口町の震度7のほか、小千谷市、山古志村(現長岡市)、小国町(同左)で震度6強と中越地方の中山間地域で強い揺れが起こり、活発な余震活動も発生して被害は甚大なものとなった。本県で発生した地震としては1964(昭和39)年の新潟地震以来の規模で、長野、群馬、福島県などで震度5弱を記録。近畿地方でも有感地震が観測された。長岡市内を走行中だった上越新幹線の車両が脱線する等、交通網は甚大な被害を受けた。

脱線した上越新幹線の車両/写真提供:長岡市
被害の特徴
余震
繰り返し規模の大きい余震が発生した。本震、余震ともにマグニチュードは6クラスだったが、震源が浅い直下型で、揺れは強烈だった。揺れの大きさは、長岡市で開業以来で初めて新幹線が脱線したことにも現れている。発生から約40分後の午後6時34分頃にはマグニチュード6.5の最大余震を観測。川口町、十日町市などを震度6強の揺れが襲った。余震は断続的に起こり、本震発生から6時間の間に震度5弱以上が10回、震度4が15回、震度2以下が119回発生した。期間も長く震度5弱以上の余震は翌日24日も1回、25日に2回など12月28日まで18回も発生した。特に発生から1週間は活発で、マグニチュード4.0以上の余震活動の回数は、マグニチュードの規模では中越地震よりも大きい1995(平成7)年の兵庫県南部地震、2,000(平成12)年の鳥取県西部地震を大きく上回った。余震活動は、本震の断層面とは別の断層面が形成されたため、全体として活発となった。

大量の土砂が川をせき止め、天然のダムが発生(山古志 木籠集落)/写真提供:長岡市
地すべり
国内でも有数の地すべり地帯の中山間地を震源とする地震だったため、地滑り、斜面の崩落が3,791カ所で発生。芋川など河川で崩壊した土砂が河川をせき止めて土石流が起き、地盤災害に伴う被害を多く受けた。長岡市妙見町の県道では大規模な土砂崩れが起きた。親子3人を乗せた車が巻き込まれ、92時間後に男の子1人が東京消防庁のハイパーレスキュー隊に救出された。山古志村(現長岡市)では各所で地滑り、土砂崩れ、河道閉塞が発生して、村につながる道路、集落をつなぐ道路が寸断。壊滅状態となって全村民の村外避難が決まり、ヘリコプターで救助された。

ヘリコプターでの避難/写真提供:長岡市
災害関連死
死者68人のうち52人が災害関連死だった。当初は避難所がいっぱいになり、余震の多さ、プライバシーの問題など避難環境の悪さも重なって車中泊をする人が増えた。同じ姿勢を長時間続けることなどで起きる「エコノミークラス症候群(肺動脈塞栓症)」の疑いが原因による死者に注目が集まった。70代以上では地震によるショックや避難生活でのストレスで心疾患や肺炎で亡くなった方も多かった。
避難所/写真提供:長岡市
被害状況
人的被害
本県における人的被害は死者が68人、負傷者が4,795人。
建物・そのほか被害
本県の住宅被害は全壊3,175棟、半壊13,810棟。一部破損は104,619棟に上った。最大で10万人以上が避難した一方で、豪雪地帯で住宅が堅牢だったため、大きな揺れの割には倒壊は少なかったと言われている。約30万戸が停電、約13万戸が断水した。同年の冬は19年ぶりの豪雪となり、家屋の倒壊や雪崩被害が地震の被害をさらに拡大させた。

仮設住宅の外観/写真提供:長岡市
復興・学び
県は「災害に強いふるさとづくり」を掲げて復興に取り組んだ。中山間地は日本の国土面積の7割を占める。全国のモデルケースになるという認識で「創造的復旧」を目指した。2005年3月に中越大震災復興基金を設置。基金規模は約3,000億円、運用規模は約600億円。災害復興基金は1991年に発生した長崎県雲仙・普賢岳の噴火火災時に設置された基金が最初とされ、中越大震災復興基金が4例目。中山間地域という特性、被災状況を踏まえ、過疎・高齢化が進行していた被災地域を反映し、生活や福祉に関する分野の支援を手厚くした。コミュニティを支援する「被災地域復興支援」という分野がもうけられたことも特徴の一つとなった。
被災地域には震災の記憶と記録を伝え、防災意識向上のきっかけとなる4施設、3公園の拠点が設置された。「中越メモリアル回廊」として結んだ各施設では復興の軌跡に触れられるだけでなく、災害に対する学びや防災人材の育成のほか、地域の交流会などに利用されている。
災害関連死で問題となったエコノミークラス症候群は、こまめな運動や水分補給で回避することができる。ライフラインが寸断され、トイレの環境が良くなかったことなどから水分摂取を控えたためエコノミークラス症候群になった人も多かった。これをきっかけに車中泊をしない、水分を取るなどの注意喚起が広まった。また簡易トイレや簡易ベッドの設置など、災害時の避難所の改善を進める動きにもつながった。

長岡震災アーカイブセンター きおくみらい/写真提供:公益社団法人 中越防災安全推進機構
参考文献・出典
- 新潟地方気象台ホームページ(https://www.data.jma.go.jp/niigata/menu/2024project/chuetsu_main.html<外部リンク>)(参照2025年03月12日)
- 新潟県ホームページ「新潟県中越大震災」による被害と復旧情報 新潟県土木部(93682.pdf)(参照2025年03月12日)
- 新潟県中越大震災記録誌編集委員会.中越大震災(前編)~雪が降る前に~.平成18年3月
- 新潟県中越大震災記録誌編集委員会.中越大震災(後編)~復旧・復興への道~.平成18年3月
- 新潟県中越大震災による被害情報(平成21年10月15日時点) - 新潟県ホームページ (参照2025年03月12日)
- 新潟県ホームページ「新潟県地域防災計画(震災対策編)」(364573.pdf)(参照2025年03月12日)