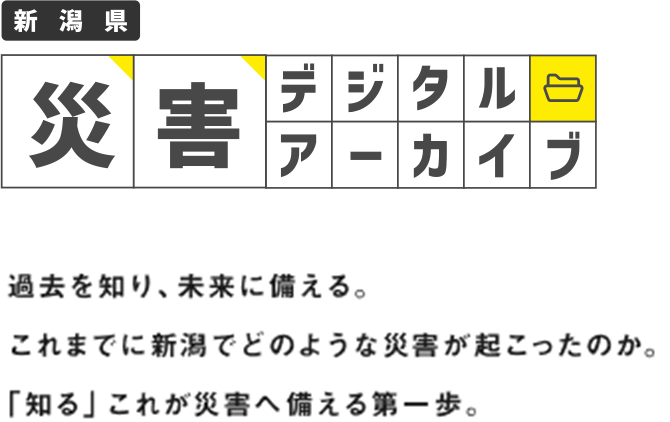本文
新潟地震

1964年6月16日


隆起した地面
災害と被害の概要
| 災害発生時刻 | 1964年(昭和39年)6月16日午後1時1分 | 最大震度 | 5 |
|---|---|---|---|
| マグニチュード | 7.5 | 最大震度発生地域 | 新潟市、相川町(現佐渡市)、長岡市 |
| 震央 |
新潟県下越沖 北緯 38度22.2分 東経 139度12.7分 |
震源の深さ | 34km |
| 人的被害 |
死者:13人 重軽傷者:315人 |
建物被害 |
全壊:1,448棟 半壊:5,376棟 全焼:290棟 半焼:1棟 床上浸水:9,446棟 床下浸水:5,544棟 一部損壊:19,472棟 |
1964(昭和39)年6月16日午後1時1分、新潟県下越沖を震源とするマグニチュード7.5、最大震度5の地震が発生。当時は関東大震災(1923年)のマグニチュード7.9に次ぐ規模だった。震源の深さは34km。発生した津波は北海道から島根県まで広い地域で観測され、本県では上海府地区(現村上市)で最大3.9メートルに及んだ。本県のほか、山形、宮城、福島県で震度5を記録し、北海道から四国地方にかけて震度を観測した。新潟市では液状化現象や製油所の火災が起き、大きな被害を受けた。

被害の特徴
液状化現象
新潟市で地面から砂を含んだ泥水が噴き上がる液状化現象が広範囲で発生した。液状化は建物に大きな被害を与え、信濃川沿いに位置する川岸町の4階建て鉄筋コンクリートのアパートは無傷のまま横転。地震被害と液状化現象の関連が注目され、地盤の液状化が防災上の課題として認識されるきっかけとなった。同年に開催された国民体育大会に合わせて半年前に竣工したばかりの昭和大橋は、信濃川に崩れ落ちた。建物だけでなく、道路は泥水が噴き出したり、亀裂が生じたりし、鉄道も線路の陥没などで寸断された。
 崩れた川岸町アパート
崩れた川岸町アパート
 崩れた昭和大橋
崩れた昭和大橋
火災
火災は一般住宅からの出火はほとんどなかったが、発生直後に国内の史上最大級の石油コンビナート火災と呼ばれる昭和石油新潟製油所の大規模火災が起きた。パイプが破損してガソリンが噴出し、タンクの貯蔵油も流出。津波による浸水などで油が浮遊して火災が広がった。石油タンクから次々と発火し、巨大な黒煙がもくもくと上がった。周辺の民家に延焼して平和町、船江町一帯の住宅などが焼け落ちた。発生から5日後にようやく延焼は食い止められたが、鎮火までは約2週間を要した。
 石油コンビナート火災
石油コンビナート火災
津波
液状化の被害に加え、信濃川に津波が流れ込み、新潟市の中心市街地は甚大な浸水被害に遭った。市街地は長年の地盤沈下で生じた海抜0メートル地帯で、護岸や河川の堤防の破損などによって1か月ほど水が引かずに被害は長期化し、5,000㏊以上の地域で浸水した。

被害状況
人的被害
本県の人的被害は死者が13人、負傷者が315人と、被害のあった9県の中で最も多かった(全体では死者26人、負傷者447人)。
建物・そのほか被害
本県の建物被害は全壊1,448棟、半壊5,376棟。床上浸水9,446棟、床下浸水5,544棟。一部破損は19,472棟に上った。耕地被害が大きく、水田の流失・埋没は3,624㏊、冠水は2,111㏊。道路は759カ所、橋は67カ所、崖崩れは111カ所、鉄道は86カ所、通信施設は2万3114回線が被害を受け、ライフラインが大きく損害した。被害世帯数は1万6,357世帯、被害者の概数は7万8,566人だった。震源に近い粟島では東海岸で約1.5メートル隆起した。

復興・学び
当日午後6時に新潟市に災害救助法の適用を決定。被害が明らかになると県内の23市町村に同法が適用された。発生から2週間後には国が激甚災害法の適用を決めた。ライフラインは、電力の供給が翌17日にはほとんどが平常に戻り、配電網が寸断された新潟市内も発生から3日後の19日には一部地域を除いて供給された。信濃川下流の堤防閉め切り作業は翌週23日までに完了し、その後排水作業を開始。その間に電話、鉄道、道路の復旧も進み、6月末には緊急を要する応急措置がほぼ終了した。県は同年7月1日に新潟地震災害復興委員会を設置し、災害復興計画の策定に着手。高度経済成長期の日本で近代化した都市を襲った初めての地震だったことから、地域的な復興としてではなく、国の将来につながる問題として、全国的なモデル防災都市の建設を目標に復興計画が進められた。被災地域の将来の経済発展も見越して約4カ月後にまとめられた計画にはバイパスや高速道路、公園整備などの都市計画が描かれた。復興計画の事業費は、国や県、市町村が主体となって行うものは約882億円、民間主体が約1,207億円で、計2,089億円に上った。
新潟地震をきっかけにできたのが地震保険だ。被災者の生活安定を目的として、1966(昭和41)年に創設。それまで災害を補償する保険は火災保険があったが、地震や噴火、津波による火災、損壊は対象ではなかった。大地震では多額の保険金支払いが発生し、民間の損害保険会社だけでは引き受けが困難だったことが要因だった。そこで民間の損害保険会社の負担を超えるリスクを政府が再保険によって分担して引き受ける官民共同の保険として、地震保険制度がつくられた。
鉄筋コンクリートアパートが基礎ごと地面から浮き上がって横転する事態を引き起こした液状化現象は、災害を契機に研究が本格的に開始されるようになり、都市開発や構造物の耐震設計などに影響を与えた。
信濃川下流の護岸、堤防が損傷したところに津波が押し寄せて水位が上昇し、新潟市街地に大きな浸水被害が起きた教訓から、信濃川下流は災害復旧事業で整備された堤防が老朽化した後の改修事業で洪水に強い堤防が採用された。信濃川水門~萬代橋の約4.5km区間で地震の揺れに強い、全国初の5割勾配の緩やかな斜面が用いられた「やすらぎ堤」は1987(昭和62)年から本格整備され、市民の憩いの場となっているだけでなく都市の防災機能も果たしている。
やすらぎ堤/出典:信濃川下流河川事務所ホームページ (https://www.hrr.mlit.go.jp/shinage/shisetsu/yasu/yasuragi.html)
参考文献・出典
- 新潟地震の記録―地震の発生と応急対策―(1965年.新潟県)(参照:2025年03月12日)
- 気象庁ホームページ(https://www.data.jma.go.jp/niigata/menu/2024project/niigata_main.html<外部リンク>)(参照:2025年03月12日)
- 気象庁技術報告第43号 昭和39年6月16日新潟地震調査報告
- 新潟県ホームページ「新潟県地域防災計画(震災対策編)」(364573.pdf)(参照:2025年03月12日)
- 新潟県ホームページ「新潟県地域防災計画(津波災害対策編)」(364612.pdf)(参照:2025年03月12日)
- 新潟県ホームページ「新潟県地域防災計画(個別災害対策編【06第5章 油等事故災害流出対策】)」(364594.pdf)(参照:2025年03月12日)