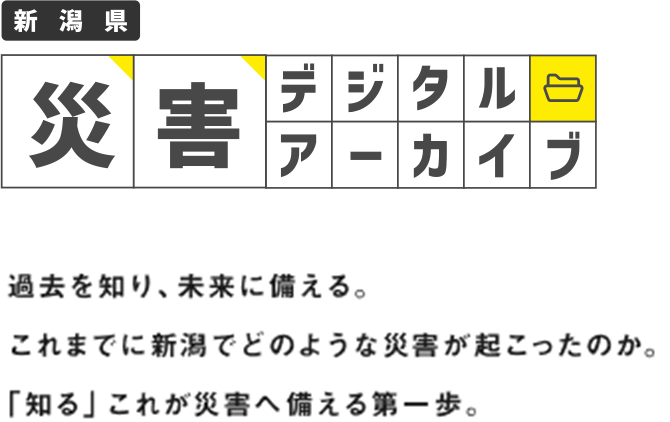本文
新潟焼山火山災害

1974年7月28日


新潟焼山 噴煙状況写真1
災害と被害の概要
| 災害発生時刻 | 1974年(昭和49年)7月28日午前2時50分頃 | 噴火場所 | 山頂部割れ目火口群 |
|---|---|---|---|
| 人的被害 |
死者:3人 |
火山活動 |
水蒸気爆発、火砕物降下、泥流 |
1974(昭和49)年7月28日午前2時50分頃、糸魚川市と妙高市にまたがる新潟焼山で水蒸気噴火が発生。付近に火口群が形成された。午前3時過ぎから1分間隔で3度の爆発を繰り返した。噴石が半径約800mの扇状の範囲に落下し、高山植物調査のためキャンプをしていた大学生3人が死亡。噴出した火山灰の総量は65万トンと推定され、新井市(現妙高市)、上越市などでは市街地が真っ白になった。中郷村(現上越市)では5mm以上の堆積があった。火山灰の噴出は断続的に3時間にわたって続き、160km以上離れた福島県まで到達した。焼山北部を流れる早川では土石流が発生。農業用水や水力発電所に影響が出た。

火山灰を被った車/出典:新潟地方気象台ホームページ(https://www.data.jma.go.jp/niigata/menu/2024project/1974_niigata-yakeyama_hunka.htm)(参照2025-03-12)
被害の特徴
活火山
標高2,400mの新潟焼山は妙高火山群の北端に位置し、火山群では最も新しく、約3,000年前の縄文時代に誕生した若い火山。たびたび噴火を起こしていて、平安時代の噴火活動の状況が地元の資料に残っている。1949(昭和24)年に約100年ぶりに噴火。以降は水蒸気爆発などを繰り返していた。1974年7月の発生前にはいくつかの兆候が観測された。4月下旬には溶岩ドーム付近に地熱の上昇によって発生したとみられる泥流が流れた跡を確認。5月には新しい噴気孔からの水蒸気噴煙、6月には噴煙量の増大と噴火口の位置の変化、7月には白煙を噴き上げている無数の噴気孔を確認している。発生前日の27日に妙高高原町役場が新井警察署(いずれも当時)と協議して登山禁止を決定したが被害が出た。
これ以降も小規模の水蒸気爆発が起き、最近では2016(平成28)年に火山灰や泥水の流出が認められた。

新潟焼山 噴煙状況写真2
被害状況
人的被害
死者3人。高山植物調査で登山していた千葉大の学生3人がキャンプ中に噴火に遭遇した。
建物・そのほか被害
最大径50cmの噴石が半径800mの範囲に落下。水田などに火山灰が降り注いだが雨によって流され、一部を除き作物に直接の大きな被害はなかった。土石流によって農業用取水口が埋設し、農地に影響が出た。
復興・学び
県は1995~96(平成7~8)年にかけて新潟焼山砂防基本計画を策定。土石流や火砕流、溶岩流などの異常な土砂流出による災害から人名や建物を守るため、砂防えん堤などの施設整備を進めている。火山活動の監視と土砂移動現象の観測を行う「新潟焼山火山監視システム」も整備し、火山活動状況を把握している。糸魚川市とともに「火山防災マップ」と「火山防災ハンドブック」を作成して市民に配布している。
2009(平成21)年には気象庁の火山噴火予知連絡会が新潟焼山を「近年噴火活動を繰り返している火山」として監視活動を強化すべき火山に選定。山麓に地震計、傾斜計、土石流監視センサーなどが設置され、火山活動を24時間体制で監視している。その後、2013(平成25)年に県や周辺自治体、国の関係機関、有識者が連携する「新潟焼山火山防災協議会」が設立され、火山活動の活発化、噴火に備えて防災・減災への体制を強化。監視データを基に火山警戒レベルを発表し、住民や登山者に早期警戒情報を発信している。

冬の焼山1

冬の焼山2
参考文献・出典
- 気象庁ホームページ;新潟焼山 有史以降の火山活動(https://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/307_Niigata-Yakeyama/307_history.html<外部リンク>)(参照2025-03-12)
- 新潟地方気象台ホームページ;新潟焼山1974年噴火 昭和49年(1974年)噴火の概要(https://www.data.jma.go.jp/niigata/menu/2024project/1974_niigata-yakeyama_hunka.htm<外部リンク>)(参照2025-03-12)
- 新潟県ホームページ「新潟県地域防災計画(個別災害対策編【04第3章 火山災害対策】)」364592.pdf(参照2025-03-12)