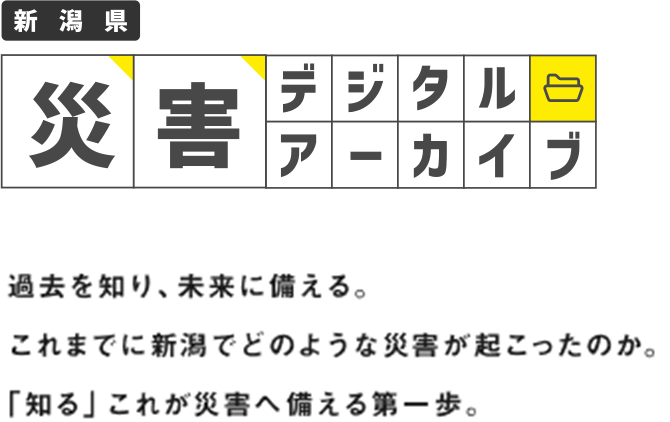本文
新潟県中越沖地震

2007年7月16日


提供:一般財団法人消防防災科学センター
災害と被害の概要
| 災害発生時刻 | 2007年(平成19年)7月16日午前10時13分 | 最大震度 | 6強 |
|---|---|---|---|
| マグニチュード | 6.8 | 最大震度発生地域 |
長岡市、柏崎市、刈羽村 |
| 震央 |
新潟県上中越沖 北緯 37度33.4分 東経 138度36.5分 |
震源の深さ | 17km |
| 人的被害(県内) |
死者:15人 重軽傷者:2,331人 (重傷者341人、継承者1,975人) |
建物被害(県内) |
【住家被害】 全壊:1,331棟 半壊:5,710棟 一部損壊:37,277棟 【非住家被害】 31,590棟 |
2007(平成19)年7月16日午前10時13分、新潟県上中越沖を震源とするマグニチュード6.8の地震が発生。長岡市、柏崎市、刈羽村と長野県上水内郡飯綱町で最大震度6強を記録したほか、県内では上越市、小千谷市、出雲崎町で震度6弱の揺れが観測された。本県で震度6弱以上の地震は、2004(平成16)年の中越大震災以来。余震は本震発生から1週間で震度6弱が1回、震度4が4回観測されたが、中越大震災と比べれば弱く、短時間で減衰した。柏崎では高さ約1メートルの津波を観測した。柏崎刈羽原子力発電所では設計時の想定を大きく超える揺れを観測。運転・起動中の2、3、4、7号機は自動停止したが、3号機の所内変圧器で火災が起きるなどトラブルが起きた。
被害の特徴
建物被害等
住宅に被害が集中した。地震の発震機構は北西―南東方向に圧縮され、断層沿いに上下にずれる「逆断層型」で地殻内の浅い地震であり、同年3月25日に発生した能登半島地震と同様のメカニズムだった。ただ、震動の激しさを表す数値として使われる最大加速度で比べると、同じ震度6強でも能登半島地震の輪島市が473.7galに対し、中越沖地震の柏崎市は1018.9galと大きかった。それに加えて周期1~2秒のやや短周期の震動により、木造家屋を中心に住宅被害が大きくなった。また、柏崎市の被害の中心地は日本海に近いため砂地が多く、液状化が発生。個人の住宅や宅地・商店街に地盤災害が広がり、擁壁や斜面の崩壊、クラックの発生なども多かった。

倒壊し、道路をふさいだ家屋の写真/写真提供:柏崎市
世界最大の柏崎刈羽原子力発電所では、所内変圧器の火災、微量の放射線物質放出のトラブルが発生。起動操作中だった2号機、運転中だった3、4、7号機は自動停止し、その後の安全確保機能は維持された。同じ中越地方で発生した中越地震からわずか3年での大規模地震が発生したこと、「日本海東縁部ひずみ集中帯」、「新潟―神戸ひずみ集中帯」と呼ばれる日本列島で特に地殻のひずみが大きいとされている帯状の領域が地震発生に関係していると考えられ報道されたことから、本県の安全イメージの悪化につながり、観光客の激減など全県的に風評被害が生じた。

クリーンセンターかしわざきの煙突の破断と大きく陥没した道路/写真提供:柏崎市
土砂災害
海岸沿いに位置したJR信越本線の青海川駅が、大規模な土砂崩壊に遭った。駅構内のホームなどが土砂に巻き込まれ、県内鉄道の全区間転再開まで約2カ月を要した。柏崎市の笠島と米山では市道が塞がるほどの大きな斜面の崩壊が起き、柏崎市を中心に地すべり26件、崖崩れが82件発生。通行止めは37か所で、生活インフラに影響を与えた。
被害状況
人的被害(県内)
人的被害は死者が15人で、そのうち65歳以上が10人を占めた。負傷者が2,331人。その多くが柏崎市内だった。

出典:国立教育政策研究所ホームページ (https://www.nier.go.jp/shisetsu/pdf/chuetsuokihinan.pdf)
建物・そのほか被害
住宅被害は全壊1,331棟、半壊5,710棟でそのうち大規模半壊は856棟。一部損壊37,277棟。非住家被害31,590棟で、建物被害は計75,908棟に上った。停電は8市村で約35,000戸。ガスの供給停止が約34,000戸。上下水道の断水は約59,000戸に及んだ。

出典:北陸地方整備局ホームページ(https://www.hrr.mlit.go.jp/bosai/noto-chuetsuoki_jishin/kirokushi_pdf/hp_all_noto-chuetsuoki.pdf)(参照2025年03月12日)

提供:一般財団法人消防防災科学センター
復興・学び
柏崎市の中心街にある「えんま通り」では、毎年6月に「えんま市」が開かれ、500軒近い露店が並び、20万人超の来場者で賑わう。新潟三大高市(たかまち)の一つの伝統的な市が開催される商店街は、地震で家屋や店舗が甚大な被害を受け、道路にも亀裂が入り、アーケードも壊れた。商店街では震災から1か月後に復興に向けたまちづくりの会が発足。街路整備では官・学・民による復興まちづくり会議が開かれ、早期に復興へと着手した。中心市街地には福祉介護施設など賑わいづくりの拠点や防災広場を整備。まちなみの景観は個別に進む建て替えを調整して、魅力を生み出すための仕組みを構築し、統一感のあるまちなみ形成を図った。
柏崎刈羽原子力発電所は、設計時の想定をはるかに超える揺れが観測され、活断層の評価や国のチェックの不十分さなど原子力発電所の耐震安全性への信頼が揺らいだ。地域住民から要請があるまで国から発電所の安全、避難の必要性といった情報が迅速かつわかりやすく提供されることがなかったことや、地震直後に変圧器で発生した火災への対応、危機管理体制が問題視されたことなど、いくつもの課題が浮き彫りになった。これらに対応するために県は2008(平成20)年から「原子力発電所の安全管理に関する技術委員会」の体制を強化。委員を拡充し、小委員会を設置した。当時の原子力災害特別措置法が、大規模自然災害等の発生を想定していないことが明らかになり、県は国に対して迅速・的確な情報提供、予防的な避難指示権限の強化等について要請した。また、県の原子力災害への対応を定めている「地域防災計画」や避難基本計画を見直すきっかけとなった。
参考文献・出典
- 国土交通省北陸地方整備局ホームページ(https://www.hrr.mlit.go.jp/bosai/noto-chuetsuoki_jishin/kirokushi_pdf/hp_all_noto-chuetsuoki.pdf<外部リンク>)(参照2025年03月12日)
- 新潟県中越沖地震の記録 - 新潟県ホームページ (参照2025年03月12日)
- 平成19年7月16日発生 新潟県中越沖地震記録誌 - 新潟県ホームページ (参照2025年03月12日)
- 平成19年(2007年)新潟県中越沖地震関連情報 - 新潟県ホームページ (参照2025年03月12日)
- 新潟県ホームページ「新潟県地域防災計画(震災対策編)」(364573.pdf)(参照2025年03月12日)
- 新潟県ホームページ「新潟県地域防災計画(津波災害対策編)」(364612.pdf)(参照2025年03月12日)
- 新潟県ホームページ「新潟県地域防災計画(原子力災害対策編)」(364618.pdf)(参照2025年03月12日)