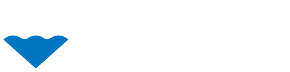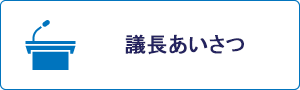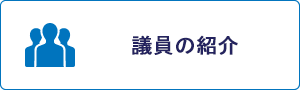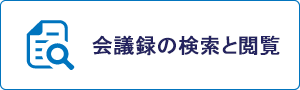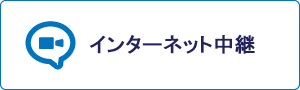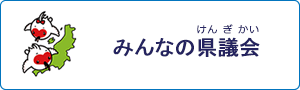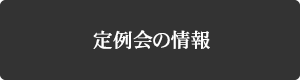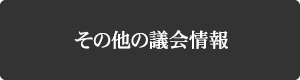本文
令和7年6月定例会(第17号発議案)
令和7年6月定例会で上程された発議案
「カリキュラム・オーバーロード」の改善を求める意見書
第17号発議案
「カリキュラム・オーバーロード」の改善を求める意見書
上記議案を別紙のとおり提出します。
令和7年7月7日
提出者 小林 誠 樋口 秀敏 上杉 知之
賛成者 諏佐 武史 土田 竜吾 笠原 晴彦
牧田 正樹 小島 晋 大渕 健
北 啓 大平 一貴 小泉 勝
杉井 旬 重川 隆広 片野 猛
柴山 唯 八木 清美 渡辺 和光
馬場 秀幸
新潟県議会議長 皆川 雄二 様
「カリキュラム・オーバーロード」の改善を求める意見書
我が国では、学習指導要領に基づき各学校が定めた教育課程の時数と内容が過多となり、子どもや教職員に過大な負担がかかる、いわゆる「カリキュラム・オーバーロード」の状態となっている。学校教育法施行規則に定める標準の総授業時数は、小学校第6学年では、平成元年の1,015時間から平成10年には945時間まで減少したが、授業時間数と指導内容を減らしたことが学力低下に結びついたとして増加に転じ、平成29年には週6日制だった平成元年と同じ1,015時間にまで増加した。中学校第3学年も平成元年の1,050時間から平成10年には980時間まで減少したが、平成20年には1,015時間に増加している。令和2年度から実施された小学校学習指導要領では、中学年に外国語活動が導入、高学年に外国語が教科化され、第3学年以上は授業時間が週1コマずつ増えたにもかかわらず、他教科の時間や内容は削られなかった。一方で、教職員の未配置、長時間労働の実態は改善されず、教材研究や授業準備の時間を十分に確保することが困難な状況となっている。
文部科学省の調査によると、令和5年度における不登校の子どもの数は小・中・高等学校を合わせると41万人を超えており、とりわけ小・中学校では11年連続で増加して過去最多となった。不登校となったきっかけ要因としては「学業の不振」や「成績の低下」、「宿題ができていない」の割合が高く、支援の方向性として授業改善や学習支援の充実を挙げており、「カリキュラム・オーバーロード」の影響が子どもたちにも表れていることを示している。
文部科学省は昨年12月、中央教育審議会に学習指導要領の改訂に向けた検討を諮問し、令和8年度中に答申が行われる見込みとなっている。学習指導要領は、子どもたちのゆたかな学びの保障や、教職員の「働き方改革」に大きく関わることから、改訂に当たっては「カリキュラム・オーバーロード」の状態を改善することが喫緊の課題といえる。
よって国会並びに政府におかれては、「カリキュラム・オーバーロード」の状態を早期に改善するため、学習指導要領の改訂に当たっては内容の精選並びに標準授業時数の削減を行うことを強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和7年7月7日
新潟県議会議長 皆川 雄二
衆議院議長 額賀 福志郎 様
参議院議長 関口 昌一 様
内閣総理大臣 石破 茂 様
文部科学大臣 あべ 俊子 様