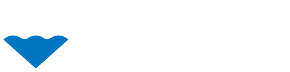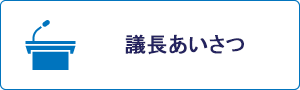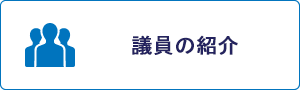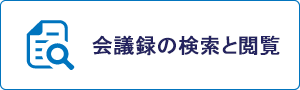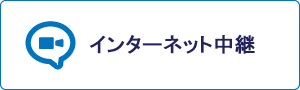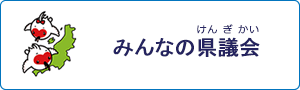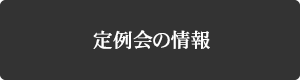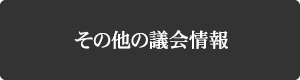本文
令和7年9月定例会(提案理由)
令和7年9月定例会提出議案知事説明要旨
議案についての知事の説明を掲載しています。
9月30日 知事説明要旨
令和7年9月定例県議会の開会に当たり、前議会以降の県政の主な動きと、提案致しております議案の概要をご説明申し上げ、議員各位並びに県民の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。
はじめに、大雨被害への対応についてです。
近年、自然災害が激甚化・頻発化しており、県内では、8月以降の大雨により、軽傷者1名の人的被害や住宅の浸水に加え、広い範囲での崖崩れや地滑り等の土砂災害のほか、道路、農地・農業用施設等に大きな被害が発生いたしました。
この大雨は、全国各地で被害をもたらしていることから、国からは、全国を対象とする激甚災害指定の見込みが示されたところです。
県といたしましては、災害による被害の早期復旧にしっかりと取り組むとともに、県民の命と暮らしを守るため、引き続きハード・ソフト両面で防災・減災対策に取り組んでまいります。
次に、県内経済の動向についてです。
本県経済は、原材料価格等の上昇による影響などがみられるものの、持ち直しの動きが続いております。一方、先行きについては、物価上昇の継続や、日米間の合意に基づく関税措置による影響が聞かれ始めており、企業収益の悪化が懸念されることから、引き続き状況を注視していく必要があるものと認識しております。
こうした中、取引適正化に向けた機運醸成を図るため、今月3日には、県が発注する全ての公共調達において重点的に取り組む内容を明記した「新潟県パートナーシップ構築宣言」を公表いたしました。県としても、適正な取引を実践していく姿勢を表明することにより、企業間における適切な価格転嫁を後押ししてまいります。
また、長期化する物価高騰や米国関税措置による県内経済への影響を最小限にとどめるため、中小企業等による生産性向上や事業再構築などのビジネス変革や、県内事業者で構成された団体による地域経済の活性化に資する取組への支援を強化することとしており、関連する補正予算案を本定例会にお諮りしているところです。
あわせて、6月にとりまとめた「米国関税措置を受けた緊急対応パッケージ」による、新たな海外販路の開拓や資金繰りへの支援についても、引き続き取り組んでまいります。
続いて、本県の主要課題について、順次ご説明いたします。
第一点目は、子育てに優しい社会の実現についてです。
先月公表された人口動態統計によれば、本県の令和7年上半期の出生数は、4,883人となっており、この傾向が続けば、昨年に続き通年で1万人を割り込み、過去最少を更新する見込みとなるなど、本県の人口は減少に歯止めがかからない状況にあります。
県では、人口減少問題を県の最重要課題として位置付け、県政のあらゆる分野の政策を総動員し取組を進めておりますが、県の取組だけでは、人口減少問題に対応していくことは困難です。
そのため、県全体で危機意識を共有し、協働して取り組んでいくため、先般、56の関係団体から賛同をいただき、「新潟県人口減少問題対策推進県民会議」を設置しました。
今後、シンポジウムの開催等を通じ、本県人口の現状や将来展望等について、県民の皆様と共有するとともに、少子化や県外流出の主たる当事者である若者との意見交換を踏まえ、施策を検討するなど、オール新潟で人口減少問題に取り組んでまいります。
本県では、就職等をきっかけとする20代前半の若者、特に女性の流出が続く中、若者や女性から選ばれる、魅力ある職場環境づくりが重要です。
このため、「多様で柔軟な働き方・女性活躍実践企業認定制度」を今年度創設し、4月以降、企業向け説明会などにより制度の周知に取り組み、半年間で300を超える企業から申請いただいたところです。
また、10月1日からの認定開始を前に、「愛称」と「ロゴマーク」を決定し、先般、公表いたしました。今後は、新しい愛称「Ni-ful(ニ―フル)」の周知・浸透を図るとともに、「ロゴマーク」の活用による認定企業の周知PRや本制度の普及・促進に努め、県内企業における魅力ある職場づくりの更なる推進に取り組んでまいります。
第二点目は、県民の安全・安心の確保についてです。
国民の防災意識の向上を目的として、国が主催する日本最大級の防災イベントである「ぼうさいこくたい」が、愛子内親王殿下の御臨席を賜り、今月6日、7日に朱鷺メッセにおいて開催されました。
過去最多となる約470の出展者による様々な防災活動の発表と交流が活発に行われ、2日間の来場者数も過去最大の約19,000人となり、大変盛況のうちに終えることができました。
大会を通じて、多くの県民の皆様から防災への関心を一層高めていただくとともに、出展団体間の交流も促進されたものと考えております。
県といたしましては、今大会を契機として、防災活動に取り組まれている様々な団体との連携などを推進し、更なる防災意識の向上と防災対策の強化に取り組んでまいります。
次に、地域医療の確保についてです。
県内の病院では、物価高騰や人件費の上昇による経費の増加などにより、極めて厳しい経営状況にあり、地域医療への影響が懸念されています。県では、これまで国に対し、足元の経営安定化に向けた緊急的な対応等を講じるよう求めてきたところであり、今後も、様々な機会を捉えて、国に働きかけてまいります。
また、経営改善を進めている県立病院や厚生連病院をはじめとした県内の病院が安定して医療を提供し続けるためには、少子高齢化に伴う医療ニーズの変化に対し、圏域全体を見据えて、適切に対応できる医療提供体制を構築していくことが一層重要になっております。地域医療構想のグランドデザインに沿って、地域の医療関係者等との協議や調整をスピード感をもって進めてまいります。
さらに、急性期等の専門的な医療を提供する病院と、日常の疾患を診療する診療所が今後も役割を分担しながら地域医療を支えていくことが必要であり、新たに、県内の医師少数区域等における診療所の承継を支援するための補正予算案を本定例会にお諮りしているところです。
県内どこに住んでいても安心して医療サービスを受けることができるよう、引き続き、取組を進めてまいります。
また、県立病院については、今年度末の内部留保資金の枯渇回避に向け、病院ごとに収支改善の数値目標を設定し、様々な取組が行われているところです。
しかしながら、第1四半期までの実績では、収支は改善しているものの、目標の達成のためには、今後、下半期において大幅な収支改善を図る必要があることから、更なる病床稼働率の向上や医療の質向上にも効果的な診療報酬の加算獲得などを中心に、病院局本庁と病院が一体となって取組を一層進めてまいります。
次に、ツキノワグマによる人身被害への対応についてです。
残念ながら、県内では9月29日現在で8名のクマによる人身被害が発生しております。今年度は、出没件数が過去最多となっていることなどから、県では、8月7日に「クマ出没警戒警報」を発表し、県民の皆様に、クマから命を守るための行動を強く呼びかけてきたところです。
また、9月1日からは改正鳥獣保護管理法が施行され、市街地にクマが出没した場合、地域住民の安全を確保した上で、市町村長の判断で発砲できる「緊急銃猟制度」が始まりました。新たな制度を円滑に運用できるよう、新発田市、県猟友会、県警、消防と連携し、現地訓練を実施するとともに、緊急銃猟制度を運用する市町村の支援を行う補正予算案を本定例会にお諮りしているところです。
今後も、県民の命を守るため、市町村や関係機関等との連携を密にしながら、クマによる人身被害の防止に努めてまいります。
第三点目は、原子力防災対策の推進と柏崎刈羽原子力発電所の再稼働問題への対応についてです。
先月、原子力関係閣僚会議が開催され、屋内退避施設や避難路の整備推進、国が前面に立った柏崎刈羽原子力発電所の監視体制の構築、原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の対象地域の概ね30km圏内への拡大など、本県がこれまで行ってきた要望を踏まえた政府の対応方針が示されました。原子力防災対策の充実・強化や東京電力の信頼確保など、県民の安全安心につながるよう関係省庁が一体となって速やかに対応を進めていただきたいと考えております。
また、原子力災害時の住民避難を円滑にするための避難路の整備等については、今月、国との第3回会合が開催されました。会合では、原子力関係閣僚会議を踏まえ、早期に着手可能な事業について、国として必要な予算を通常事業とは別枠で確保することが確認されるとともに、UPZ内の自治体からの整備要望について、今後、内容を精査していくことが確認されました。引き続き、早期の避難路の整備等に向けて、国とともに取り組んでまいります。
また、避難の実効性の確保に向けては、先月、柏崎市等において、夜間の孤立地域発生を想定したヘリコプターによる住民避難訓練を実施いたしました。今後も10月及び11月に、住民や、国、市町村等関係機関が参加する原子力防災総合訓練を実施することとしております。こうした訓練を繰り返し行うことにより、原子力災害発生時に備えた対応力の更なる向上を図ってまいります。
柏崎刈羽原子力発電所の再稼働に関する多様な意見を把握するため、先月まで開催したブロック別懇談会において、県内すべての市町村長から再稼働問題に関する率直なご意見をいただいたところです。
また、6月から8月にかけて県内5地域で開催した公聴会において、87名の公述人の方々から、賛成、反対、条件付賛否など、それぞれの立場から、理由や背景を含め様々なお考えをお聞きしました。
県民意識調査については、今月、県内の18歳以上の方を対象に、柏崎刈羽原子力発電所の安全対策や原子力災害に備えた防災対策への認識、6・7号機の再稼働に関する考え方等に関する調査を実施しました。準備が出来次第、途中経過を公表するとともに、さらに調査結果の分析を進めてまいりたいと考えております。
こうした取組に加え、県議会でのご議論などを通して、再稼働問題に関する県民の意思を見極めてまいります。
第四点目は、交流人口の拡大と賑わいの創出についてです。
「佐渡島(さど)の金山」が世界遺産に登録されてから1年が経過しました。佐渡市からは、登録後の観光目的の入込客数は、前年に比べて約1.2倍と増加傾向にあると伺っており、登録による一定の効果が出ているものと承知しております。
県では、この効果をさらに県全体に波及させるため、6月から県内宿泊事業者と連携し、世界遺産登録1周年を記念するキャンペーンを実施しているほか、各種メディアを通じた情報発信を強化しているところです。
今後も、市町村や観光関係者と連携し、「オール新潟」でプロモーションの強化に取り組み、世界遺産のブランド力を最大限活用しながら、本県への誘客拡大と周遊促進を図ってまいります。
また、佐渡市と連携し、「佐渡島(さど)の金山」保存活用推進ネットワークの枠組等を活用しながら、地域社会総がかりでの適切な保存修理や公開活用を、引き続き推進してまいります。
次に、大阪・関西万博についてです。
6月10日から実施した「食と暮らしの未来」をテーマとした本県催事には、開場前から行列ができるなどの賑わいも見られ、4日間で約5万人の来場があり、県内企業が開発した新潟発の未来の食などを体験いただきました。
また、7月13日から実施した、伝統工芸品やデジタル技術を活用した錦鯉・花火の展示では、約2万4千人の方から県産品に実際に触れて体感いただくなど、県内各地の多様な魅力を広く発信してまいりました。
県といたしましては、万博の成果を交流人口の拡大につなげるため、万博の発信力も活用し、高付加価値旅行商品の販売やアンテナショップを活用した県産品のプロモーションなどに取り組んでまいります。
次に、妙高地域における大規模リゾート開発についてです。
7月に、県、関係市町村をはじめ、交通事業者、金融機関及びPCG等を構成団体とする「妙高杉ノ原マウンテンリゾート開発計画連携地域活性化協議会」の第1回会合を開催いたしました。会合では、PCGが掲げる「地域とともに持続的に発展する」という理念や開発計画を共有するとともに、官民連携の取組や課題等について意見交換を行ったところです。
その後、構成団体である、えちごトキめき鉄道、頸城自動車、佐渡汽船の3社においては、「佐渡島(さど)の金山」の世界遺産登録や、妙高リゾート開発の動向を見据え、協力して広域観光の促進や公共交通の利便性向上等を図るための連携協定を締結されたとお聞きしております。
今後も協議会の枠組みを活かしながらPCGの計画実現を後押しし、上越圏域の経済活性化を図るとともに、県全体の活性化にもつなげていけるよう取り組んでまいります。
次に、8月でグランドオープンから1周年を迎えた「銀座・新潟情報館 THE NIIGATA」についてです。
オープン以降、本県の多様な魅力を発信するとともに、市町村と連携したイベントやビジネス商談会の開催などにより、この1年間で44万人以上のお客様から来館いただき、販売額についても運営事業者の想定を概ね達成しております。
また、1周年記念イベントでは、本県出身のタレントから名誉館長に就任いただくとともに、長岡花火のパブリックビューイングや工芸品の体験型ワークショップなどにより、「THE NIIGATA」の話題づくりにも取り組んだところです。
今後も、情報発信拠点の目的である新潟への人の動きを作っていくため、県産品の認知度向上や販路拡大、交流・体験イベントの開催などを通じて、本県ならではの魅力を発信し、多くの方々から愛される拠点となるよう努めてまいります。
次に、モンゴル及び韓国訪問についてです。
去る8月19日から23日にかけて、モンゴルと韓国を訪問いたしました。
モンゴルについては、日本とモンゴルを結ぶ初めてのチャーター便が新潟から運航し35年の節目となる今年、チャーター便が運航する機会をとらえ、新旧の在新潟モンゴル国名誉領事や関係自治体、教育機関等とともに訪問したところです。
現地では、新潟県立大学とモンゴルとの教育研究交流拠点となる、新潟県立大学モンゴルオフィスの開所式や、新潟米のPRイベント「ライス・エキスポ」に参加しました。
「ライス・エキスポ」では、開催2日間で約1万人の方から来場いただき、「雪に育まれる新潟の魅力」をテーマに、新潟米をはじめ、本県の食や観光資源の魅力をPRしたところです。
また、モンゴル外務省の幹部や、県内大学に留学経験があり前政権で副首相を務めた国会議員等とも面会し、人的交流の必要性について認識を共有するなど、モンゴルとの交流の土台を、より強固なものにする機会になったものと考えており、留学生等の人的交流や県産品の輸出促進などに、より一層取り組んでまいります。
また、韓国では、航空会社や現地旅行社を訪問し、ソウル線の増便や利用促進に対する協力を要請してきたところであり、引き続き、イン・アウト双方向の更なる利用者拡大に取り組んでまいります。
第五点目は、鉄道ネットワークの整備についてです。
新潟地域と上越地域のアクセス改善に向けて、在来線の高速化を図り、幹線鉄道ネットワークを整備することは、国土強靱化や日本海国土軸の形成の観点から重要と考えております。先月開催した「高速鉄道ネットワークのあり方検討委員会」においては、4つのルート案の需要予測などが報告されたところです。今後、さらに、事業による経済波及効果などの調査・検討を深めていくとともに、引き続き、国に対して高速化の実現に向けた働きかけを行ってまいります。
併せて、今年度、交通事業者や沿線自治体等と連携し、特急しらゆきについて、乗車券と指定席特急料金から50%の割引きを実施するとともに、高速バスについても、2名以上の利用で運賃から最大50%の割引きを実施するなど、両地域を結ぶ幹線交通の利用促進に向けた取組を進めております。こうした取組を通じて、公共交通の利用への行動変容を促し、利用者数の増加を図ることにより、将来の幹線交通の利便性向上につなげてまいります。
次に、米坂線の復旧についてです。
今年8月で被災から3年が経過しました。先月の復旧検討会議において、4つの復旧パターンのうち、上下分離、地域鉄道及びバス転換における復旧後のイメージや利便性向上策などがJRから示されました。
県といたしましては、できるだけ速やかに復旧への道筋が得られるよう、今後、地域においてどのような公共交通が望ましいのか、沿線自治体や交通事業者とともに、地域での検討をさらにスピード感を持って進めてまいります。
第六点目は、付加価値の高い持続可能な農林水産業の実現についてです。
主食用米の価格高騰が続く中で、本県の生産現場においては主食用米の生産意欲が高まり、6月末時点の作付意向では、主食用米の作付面積が前年実績から約7千ヘクタールの増加となっております。
一方、加工用米などの非主食用米等の作付面積は前年に比べて減少する見込みであり、県内に集積する食品事業者や海外からの需要にもしっかりと応えながら、主食用米と非主食用米を合わせた新潟米全体で水田所得の最大化を進めていくことが重要です。
このため、先般、生産者やJAグループ、流通事業者、米関連事業者と、今般の米価高騰を踏まえた需要に応じた米の生産・流通のあり方や課題等について意見交換を行ったところです。いただいたご意見を踏まえ、持続可能な水田農業の実現に向けた施策や、国が検討を進める令和9年度の水田政策の見直しに向けた、本県としての要望内容の検討を進めてまいります。
また、今後も主食用米の価格の高止まりが継続すれば、生産現場において酒造好適米から主食用米への作付転換が一層進み、次年度以降の酒造好適米の生産減少が懸念されます。
新潟米と新潟清酒は本県を代表する特産品であり、農業と酒造業が共に発展することが重要であることから、新潟清酒の製造に欠かせない酒造好適米の安定生産・供給と、県内での持続可能な酒造りを両立させていくことが必要です。
このため、酒造好適米の生産が、作期分散や事前契約による安定収入など、水田農業経営の安定化につながることを改めて農業者にお示ししながら、農業と酒造業の結びつきの強化を図ってまいります。
また、令和7年産の酒造好適米の価格が高騰していることから、その影響を緩和し、県内酒蔵における高品質な新潟清酒の生産を後押しするため、関連する補正予算案を本定例会にお諮りしているところです。
第七点目は、公民協働プロジェクトの推進についてです。
県では、令和元年に「公民協働プロジェクト検討プラットフォーム」を設立し、取組を進めておりますが、このプラットフォームでの意見交換を契機として、民間の長期投資プロジェクト等を官民連携で後押しし、本県の地域経済や社会の活性化につなげるため、この度、県や県内金融機関等が出資する「にいがたサステナブル地域創生ファンド」が設立されたところです。年度内には、観光や脱炭素・エネルギー分野などの県内プロジェクトへの投資を想定しており、持続可能な経済成長と地域の面的活性化につなげてまいりたいと考えております。
また、港湾緑地における賑わい創出に向け、新潟港万代テラスにおいて、全国で3か所目となる「みなと緑地PPP」を活用した取組を進めています。港湾緑地の長期貸付により民間事業者が賑わい空間の創出を図る港湾環境整備計画を8月に認定したところであり、来年春のオープンを目指して、事業者が準備を進めているところです。
県立都市公園では、利用者の利便性向上と公園の魅力向上に向けPark-PFI制度の導入を進めています。公募条件が整った鳥屋野潟公園の鐘木地区において、現在、事業者の公募を実施しているところであり、年度内の決定に向けて取り組んでまいります。
さらに、官民が連携して維持管理等の一体的なマネジメントを行うウォーターPPPについては、流域下水道事業への導入に向けて、現在、公募条件を検討しているところです。
県といたしましては、こうした民間が有する人材や知見、ネットワーク、資金等のリソースを積極的に活用し、公民協働による取組を推進することで、本県経済の活性化や活力づくりにつなげてまいります。
第八点目は、北朝鮮による拉致問題についてです。
曽我ひとみさんら5人の帰国から23年が経とうとしていますが、未だ解決に向けた具体的な進展は見られず、拉致被害者やそのご家族の高齢化が進む中、もはや一刻の猶予も許されない状況にあります。
8月に行われた日韓首脳会談では、拉致問題の解決に向けた理解と協力について、李韓国大統領から支持を得たとされ、また、同月の米韓首脳会談においてトランプ米国大統領は、米朝首脳会談の早期実現に意欲を示されています。
政府には、特定失踪者も含め、拉致被害者やそのご家族の差し迫った思いをしっかり受け止め、米国や韓国をはじめ、国際社会と緊密な連携を図りながら、日朝首脳会談を早期に実現し、全ての拉致被害者の一日も早い帰国につながるよう、全力で取り組んでいただきたいと思います。
県といたしましては、今後も、国へ働きかけるとともに、「新潟県拉致問題等の啓発の推進に関する条例」を踏まえ、11月の「拉致問題等啓発月間」において、県民集会や若年層向けのオンラインセミナーを実施するなど、市町村や教育機関等と連携し、啓発に取り組んでいくことにより、拉致問題の早期解決に向けた気運の醸成を図り、政府の取組を後押ししてまいります。
最後に、行財政運営についてです。
先般お示しした中期財政収支見通しでは、人件費や金利上昇の影響、国の経済見通しなどを踏まえ再算定した結果、前回と同様、大規模災害等に備えるための財政調整基金を230億円確保するとともに、令和13年度の公債費の実負担のピークに対応できる見込みとなっています。
しかしながら、今後の経済状況や国の地方財政対策の動向などによっては収支の大きな変動も想定されることから、引き続き堅実に収支を見通しながら、持続可能な財政運営の実現に向けて取り組んでまいります。
次に、「県庁の組織風土・内部統制に関する有識者会議」の提言を踏まえた取組についてです。
有識者会議では、本事案に至った背景を含め、県庁全体の組織風土の問題点や内部統制における課題、及び再発防止策について、昨年6月から1年以上にわたり丁寧に調査・検討を行っていただきました。
今月1日に提出された報告書では、本事案の背景・課題として、所属長が孤立し、他者への相談がしにくかったことや、利害関係者への対応ルールが徹底されていなかったことなど、県の組織としての問題点について指摘がなされました。
あわせて、再発防止に向け、不当な要求に臆することがないようトップメッセージを発信することや、コンプライアンス意識の徹底などの提言をいただいたところです。
県といたしましては、これらの指摘や提言を真摯に受け止め、こうした事案が二度と発生しないよう、県庁全体として継続的に再発防止策を実行してまいります。また、私といたしましても、職員に対し、相談しやすい環境づくりに取り組むことや、不当な要求に毅然とした態度を取ることなど、繰り返しメッセージを伝えてまいります。
続いて、提案しております主な議案についてご説明申し上げます。
第111号議案は、一般会計補正予算案でありまして、総額68億3,896万4千円の増額補正についてお諮りいたしました。
今回の補正は、エネルギー価格・物価高騰の影響を受けている生活者及び事業者等に対する支援に必要な経費や、地域の渇水対策や災害対応に要する経費等について計上したところです。
その結果、補正後の予算規模は、1兆2,723億6,747万5千円となります。
次に、その他の主な条例案件等についてご説明申し上げます。
第117号議案は、県立高校等再編整備計画に基づき、県立柏崎高等学校附属中学校及び県立碧高等学校を設置するため、条例の所要の改正を行うものです。
次に、第118号から第120号までの各議案は、契約の締結について、第121号議案及び第122号議案は、損害賠償額の決定について、第123号から第126号までの各議案は、権利の放棄について、お諮りするものです。
最後に、第127号から第133号までの各議案は、企業会計に係る決算の認定及び利益剰余金の処分について、お諮りするものです。
以上、主な議案の概要につきまして、ご説明申し上げましたが、何とぞ慎重にご審議のうえ、各議案それぞれについて、ご賛同を賜りますよう、お願い申し上げます。
10月20日 知事説明要旨
ただいま上程されました第134号議案は、令和6年度一般会計及び特別会計の決算の認定について、お諮りするものであります。
よろしくご審議のうえ認定を賜りますようお願い申し上げます。
10月21日 知事説明要旨
ただいま上程されました議案2件は、いずれも人事に関する案件であります。
第135号議案は、教育委員会委員を任命するため、第136号議案は、公安委員会委員を任命するため、それぞれお諮りいたしました。
よろしくご審議のうえ同意を賜りますようお願い申し上げます。
令和7年9月定例会・議会情報項目一覧へ
新潟県議会インターネット中継のページへ<外部リンク>
新潟県議会のトップページへ