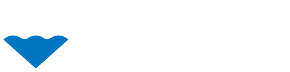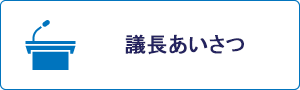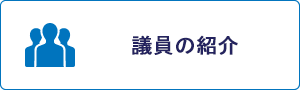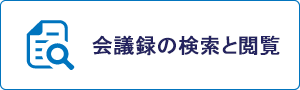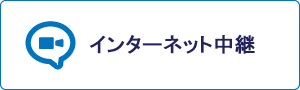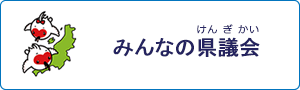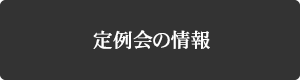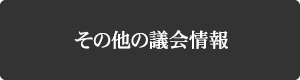本文
令和2年2月定例会(第7号発議案)
令和2年2月定例会で上程された発議案
選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書
第7号発議案
選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書
上記議案を別紙のとおり提出します。
令和2年3月19日
提出者 池田 千賀子 上杉 知之 大渕 健
賛成者 樋口 秀敏 小島 晋 高倉 栄
長部 登 小山 芳元 小泉 勝
杉井 旬 重川 隆広 秋山 三枝子
片野 猛 市村 浩二 安沢 峰子
遠藤 玲子 佐藤 浩雄 小島 義徳
佐藤 久雄 渡辺 和光 飯野 晋
新潟県議会議長 岩村 良一 様
選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書
平成30年2月に内閣府が公表した世論調査では、夫婦同姓も夫婦別姓も選べる選択的夫婦別姓制度の導入に賛成・容認と答えた国民は66.9%となり、反対の29.3%を大きく上回ったことが明らかになった。特に、30歳代における賛成・容認の割合は84.4%になる。
平成30年3月20日の衆議院法務委員会における政府答弁によると、法律で夫婦同姓を義務付けている国は日本だけであるにもかかわらず、平成8年に法制審議会が、いわゆる選択的夫婦別姓制度の導入を含む「民法の一部を改正する法律案要綱」を答申してから24年、いまだ法改正の見通しは立っていない。
また、最高裁判所は平成27年12月、民法の夫婦同姓規定を合憲とする一方で、夫婦同氏制の下においては、婚姻によって氏を改める者にとって、アイデンティティの喪失感を抱くなどの不利益を受ける場合があることは否定できず、妻となる女性が不利益を受ける場合が多いことが推認できるとして、婚姻に伴う改姓により一定の不利益が生じる可能性を認め、「制度の在り方は、国会で論ぜられ、判断されるべき事柄」とし、夫婦別姓を導入することを否定していない。
家族の多様化が進む中、旧姓を通称使用する人や事実婚を選択するカップルも少なくない。また、改姓によって、これまで築き上げたキャリアに分断が生じる例や、結婚を諦める例なども見られ、不利益を被る人が一定数いることも事実である。このため、選択的夫婦別姓については、最高裁判決の趣旨を踏まえ、適切な法的選択肢を用意することが国会及び政府の責務である。
よって国会並びに政府におかれては、選択的夫婦別姓制度を導入する民法の改正を行うよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和2年3月19日
新潟県議会議長 岩村 良一
衆議院議長 大島 理森 様
参議院議長 山東 昭子 様
内閣総理大臣 安倍 晋三 様
法務大臣 森 まさこ 様