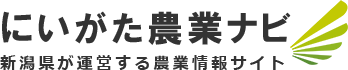本文
【地域の普及活動】十日町農業普及指導センターの取組を紹介します
十日町農業普及指導センターの取組を紹介します
そばの生産向上に向けて
十日町地域は県内でも有数のそばの産地です。そばの収量・品質向上に向け、生産者による栽培方法の試行錯誤が続けられており、普及指導センターは、技術指導を通じて、その活動を支援しています。
今年度は、収量低下に悩む生産者に対し、慣行の配合肥料を緑肥(ヘアリーベッチ)で代替することによって、生育や収量にどのような差が出るか調査しています。
そばの成熟期調査
新そばの季節になりました。ぜひ十日町へ足を運んで、旬の味覚をご賞味ください。
2025年11月
河田 典
地域に貢献できる普及指導員を目指して
十日町農業普及指導センターの伊藤 萌々香です。
4月より新採用職員として配属され、野菜を担当しています。

ねぎの生育調査の様子
写真は、当地域において出荷が11月となるねぎ品種を選定するための栽培実証を行っている様子です。
現在はまだ、先輩普及指導員と共に現地を回り、十日町地域の農業について学んでいる段階ではありますが、一日でも早く地域に貢献できるよう精一杯取り組んでいきたいと思います。
2025年8月
伊藤 萌々香
地域が目指す10年後の姿の実現に向けて(十日町市六箇地区)
ビレッジプラン2030の重点地区である十日町市六箇(ろっか)地区では、将来プランに位置付けた「定住につながる仕組みづくり」、「地区の魅力発信と交流の場づくり」の先行取組として、花ハス栽培や花ハスの加工品(プリザーブドフラワー)の販売による休耕田の活用と地域ブランドづくりの他、日本大学芸術学部の学生との十日町雪まつりの雪像づくりやプロジェクションマッピングの活用など、地区住民と地区外の学生や観光客等来訪者との交流を行ってきました。

地区の活動等をプロジェクションマッピング

AR(拡張現実)技術を雪像に活用
また、令和6年に着任した地域おこし協力隊員が講師となり、地域住民を対象としたAI教室の開催の他、3月には地元小学生を対象とした「春のマンガ図書館まつり」を開催しました。子どもたちは最新のAIと会話してみたり、好きなページの絵を描いたりと楽しみながら時を過ごしていました。
春のマンガ図書館まつり
同地区では、令和7年度も花ハスやマンガ図書館の活用、デジタル技術を使った地域おこしなどの取組を行う予定です。
十日町農業普及指導センターでは、地区の自主的な活動を関係機関とともにサポートしていきます。
2025年5月
中村 正安
▼地域おこし協力隊について
地域おこし協力隊は、都市地域から過疎地域等の条件不利地域に住民票を異動し、地域ブランドや地場産品の開発・販売・PR等の地域おこし支援や、農林水産業への従事、住民支援などの「地域協力活動」を行いながら、その地域への定住・定着を図る取組です。隊員は各自治体の委嘱を受け、任期はおおむね1年から3年です。
川手地区の集落機能及び農業の維持に向けて魅力発信!
十日町農業普及指導センターでは、集落機能及び農業の維持に向け、十日町市川手(かわて)地区が策定した将来プランの実践活動を支援しています。
川手地域づくり協議会が主体となり、(1)地区の魅力発信、(2)美人林直売所の活性化、(3)川手産米の収量・品質・食味向上などに取り組んでおり、担当普及員として稲作指導の他、先進地視察や今後の体制づくりに向けた話合いのフォローなどをしてきました。
川手地区作柄検討会の様子
今年の2月には、地区の魅力発信の一環として川手地区を紹介するHPが公開されましたので、是非、チェックしてみてください。

川手地区公式HP
(https://matsunoyama-kawate.com/<外部リンク>)
2025年3月
永井 翔大