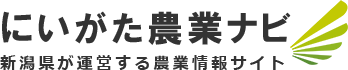本文
【地域の普及活動】新発田農業普及指導センターの取組を紹介します
新発田農業普及指導センターの取組を紹介します
和牛子牛の発育向上を支援しています
新発田農業普及指導センターで、主に阿賀野市の畜産を担当している2年目の富樫です。
近年、管内の子牛生産農家が出荷する子牛の発育に差があり、収益性等の低下が心配されています。
そのため、子牛が順調に育っているかを把握するために体重や体格の測定を定期的に行い、子牛への哺育技術(ミルクの飲ませ方)の改善に向けたアドバイスを行っています。

和牛子牛の体格を測定しています
2026年1月
富樫 怜
果樹若手生産者を応援する学びの場
新発田農業普及指導センターで果樹の担当をしている橋本です。
他の作目と同様、果樹でも地球温暖化による異常気象により、毎年様々な問題や経験したことのない事態が発生しています。特に、近年就農した若手生産者はまだ経験年数が浅いため、収量や品質の確保に日々奮闘しています。
そこで、その手助けとなるようベテラン農家を塾長とするぶどうの園芸参入塾を開催し、品種や樹の仕立て方による栽培方法の違いを学ぶなど、問題に対応できる実践力を身に付けてもらえるよう支援しています。

塾長の鋏の先を見つめる塾生達
この学びの場が、経営の発展や仲間づくりに少しでも役立つよう、これからも塾生をサポートしていきます。
2025年10月
橋本 麻衣
▼園芸参入塾について
農業経営の幅を広げる園芸の導入・拡大を志向する農業者等を対象に新潟県が行う実践的、専門的な研修のこと。野菜、果樹、花き等の専門部門について、高度先端知識や技術を学ぶことができる。
PDCAサイクルを回そう!
新潟県農業大学校で勤務し3回卒業生を送り出した後、現普及指導センター勤務となりました。管内には、就農した教え子も数人おり、4Hクラブへの勧誘や時々情報交換を行うなど、頑張っている卒業生を応援しています。
今年は重点モデル経営体の対象法人において、新潟県農業大学校の卒業生である従業員3人の人材育成を目的に、水稲の移植及び乾田直播栽培の調査に取り組んでおり、今後は結果のとりまとめを行い、法人内での作柄検討に結びつける予定です。
PDCAサイクルを回し、法人の大事な柱になってもらえるよう活動を応援していきます。

3人協力しての乾田直播の生育調査
2025年7月
渡邉 輝彦
▼4Hクラブ(農業青年クラブ)について
若い農業者が中心となり、農業経営をしていくうえでの身近な課題の解決方法を検討したり、より良い技術を検討するためのプロジェクト活動を中心に、消費者や他クラブとの交流、地域ボランティア活動を行っている組織です。
4Hとは、農業の改良と生活の改善に役立つ腕(Hands)を磨き、科学的に物を考えることのできる頭(Head)の訓練をし、誠実で友情に富む心(Heart)を培い、楽しく暮らし、元気で働くための健康(Health)を増進するという、同クラブの4つの信条の頭文字を総称したものです。(農林水産省ホームページより一部抜粋)
えだまめブランド「えんだま」の拡大を支援しています
4月から阿賀野市(あがのし)ささかみ地区のえだまめ産地を担当している加藤です。
ささかみ地区では、平成29年度からえだまめの産地化に取り組んでいます。堆肥と米ぬか及びオリジナルえだまめ肥料の施用を必須とした環境にやさしい農業を実践しており、令和元年度からA品を「えんだま」として販売しています。販売額、栽培者も年々増加傾向にあり、若く活気のある産地です。

市場担当者と莢(さや)色に関する打ち合わせ
そんな中、私は普及員としてSNSでの情報提供や実証ほの設置、産地への技術提案などに取り組みました。また、日々の活動の中で関係者に対して頻繁に会いに行くこと、丁寧に接することを特に心掛けていました。新しい気づきや課題を得ることができるので、直接対話することは非常に大切だと感じています。

部会反省会にて 来年度に向けて一致団結!
今後も更に産地が拡大できるよう支援していきます。
2025年2月
加藤 玲