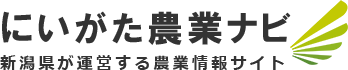本文
【地域の普及活動】佐渡農業普及指導センターの取組を紹介します
佐渡農業普及指導センターの取組を紹介します
活気ある集落を取り戻すために
佐渡市旧小木町の琴浦集落は、ビレッジプラン2030の対象地区であり、ビレッジプランの達成に向けて外部人材受入や集落活性化に向けて取り組んでいます。
集落では、特にコロナ禍以降様々な行事が縮小や中止となり、活気が低迷しています。
集落を少しでも活気づけようと、集落外住民を対象としたさつまいもの芋ほり体験交流会を集落の皆さんと共に開催しました。
芋ほり体験交流会の様子
当日は芋ほり体験の他、琴浦農業の歴史説明や琴浦で昔からさつまいもを保管する際に使用する通称”いも穴”の見学も行われ、楽しく集落外住民との交流が行われました。
今後はさらに集落が活気づくよう集落外住民との体験交流会を継続するとともに、地域の担い手として期待できる地域おこし協力隊の受入にも取組み、活気ある集落を取り戻すために普及指導センターとしても関係機関と連携しながら支援を継続していきます。
2026年2月
千野 史貴
地域の発展を支える普及活動を目指して
今年度から作物担当として佐渡地域に配属となりました、新採用職員の吉澤 槙之助(よしざわ しんのすけ)です。
普段は先輩職員に同行して、水稲を中心に大豆や麦といった作物の生育調査や指導会等を行い、普及指導員の役割について学んでいます。

研修での収穫作業
佐渡島内でも稲刈りが着々と進行し、普及センターでは佐渡地域における収量・品質に関する調査を行っています。
今後も、地域農業の維持・発展や農政課題の解決を支援する普及センターの一員として、日々精進してまいります。
2025年11月
吉澤 槙之助
佐渡地域におけるアスパラガス産地発展
佐渡地域ではおけさ柿、西洋なし、アスパラガスについて園芸産地発展ビジョンを作成し、令和14年度の販売額を現在より3割アップさせることを目指して取り組んでいます。その取り組みの一環として、アスパラガスでは担い手の確保を目的に園芸参入塾を年4回開催しています。
講師の園地にて管理方法を学ぶ塾生
座学による栽培技術学習にあわせて講師ほ場で実際の栽培を確認することで、アスパラガスの栽培技術の習得と新規導入者の経営安定を支援しています。
2025年8月
佐藤 秀明
▼園芸参入塾について
農業経営の幅を広げる園芸の導入・拡大を志向する農業者等を対象に新潟県が行う実践的、専門的な研修のこと。野菜、果樹、花き等の専門部門について、高度先端知識や技術を学ぶことができる。
佐渡における担い手の定着に向けて
佐渡地域では、「朱鷺(とき)と暮らす郷」認証米に代表される米の生産を中心に、「おけさ柿」や「ルレクチエ」といった果樹、和牛繁殖や酪農といった畜産など、多様な組み合わせによる農業経営が展開されているものの、基幹的農業従事者数は、高齢化とともに令和2年までの10年で約6割と激減している状況です。
地域農業を維持していくためには担い手の確保が喫緊の課題となっていることから、普及指導センターでは新規就農者の年間 20 人の確保を目標に掲げ、関係機関とともに担い手支援チームを作り取組を進めています。
具体的には、就農者募集パンフレットの作成、将来の就農候補者である地元高校生への出前授業の実施、佐渡市公認の求人サイト「さどマッチボックス」の活用の他、就農相談に応じた農業体験や研修先との面談、就農計画の作成支援など、関係機関と連携を強めた取組を行っています。
先輩農業者を訪問している様子
さらに、共同防除の体制が整っているかき団地での受入体制整備や、経営開始型交付対象への伴走支援、栽培技術の習得に向けた園芸参入塾や稲作講座の開催など継続した支援活動の実施により、令和元年以降の新規就農者数は年間15人前後を維持するほか、JA佐渡や羽茂農業振興公社が受入を行っている研修生を増加傾向とするなど、新規就農者の安定確保に一定の成果を見せています。
今年度も引き続き、関係機関・団体等との連携により、就農啓発と就農候補者に対する相談活動や新規就農者等の技術習得の支援など、確実な定着と経営発展に向けた指導を行ってまいります。
2025年5月
田中 雅生
佐渡南部地域の果樹発展に向けて
今年度から佐渡農業普及指導センター羽茂(はもち)分室に配属されました、江口大智です。
佐渡南部地域では、温暖な気候を活かしておけさ柿を中心にル レクチエ、黒いちじく、みかん、うめなど果樹生産が盛んに行われています。
私は果樹担当として生育調査などを通して、日々地域の果樹について学んでいます。最近では、うめのせん定作業を行いました。

せん定作業の様子
先輩や農業者の方々から日々学び、一日でも早く地域の農業の発展に貢献できる普及指導員になれるよう、努力していきます。
2025年3月
江口 大智