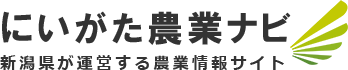本文
【地域の普及活動】長岡農業普及指導センターの取組を紹介します
長岡農業普及指導センターの取組を紹介します
雪を利用した環境に優しい小千谷市にんじん産地の取り組み
小千谷人参生産組合では自然の恵みを活かし、秋に収穫したにんじんを雪の中で一定期間保管し、「雪中(せっちゅう)にんじん」として出荷し好評を得ています。
白銀に映えるこだわりのにんじん
生産を始めた当初から使用している芯まで赤く良食味な「ひとみ5寸」にんじんは、気候変動の影響で年々、栽培が難しくなってきていますが、普及センターでは、生産者の安定生産に向けた取組をJAと共に支援しています。
降りしきる雪の中、にんじん保管庫前の園主さん
2026年2月
中村 敏子
地域農業に根差す
新採用職員として、長岡農業普及指導センター 小千谷(おぢや)分室に作物担当として配属になりました、渡邉 徹(わたなべ とおる)です。
今年は、小千谷・川口(かわぐち)地域での普及活動において、水稲を中心とした作物の栽培技術習得に励みながら、栽培技術情報等を皆さんに伝えられるよう尽力しました。

営農体験研修の様子
前職の農機具メーカーでの勤務経験を活かし、今後とも「魚沼(うおぬま)米」生産に貢献していきたいと思います。
2025年11月
渡邉 徹
収量と品質の向上を目指して
今年度から新採用職員として、長岡農業普及指導センターの配属になりました、渡邉 俊元(わたなべ としゆき)と申します。
現在は、水稲を中心に長岡地域のほ場巡回や生育調査などに同行し、業務に励んでいます。

ゆきみらいの幼穂の確認の様子
前職の下越のJAで水稲の営農指導を担当していた地域とは違うところがたくさんあり、戸惑いもありますが、新鮮さを前向きに受け止め、先輩普及指導員や農業者の方々から助言をいただきながら、知識と技術の習得に努めていきます。
2025年8月
渡邉 俊元
今年も水稲の作付が始まりました
今年も水稲の播種作業が始まりました。
私の担当する長岡市栃尾(とちお)地域では、JAが浸種、播種、加温出芽を行い、その後、管理作業の大部分を農業法人が受託し硬化まで行う体制ができています。
写真は4月にJAの育苗センターで、種子や苗の状況確認を行った時の様子です。種子ははと胸状態、出芽苗は幼芽長5mm程度となっており、いずれも生育は順調でした。
種子の催芽状況を確認する様子
出芽状況を確認する様子
また、ハウスに並んだ苗は揃いのよい素晴らしい苗でした。
揃いのよい苗
普及指導センターでは、JA等の関係機関と連携し、産米の収量・品質の高位安定を支援しています。
2025年5月
小宮 郁生
飼料費低減のため稲WCSの活用を推進しています
今年度から長岡で勤務している、畜産担当の水落です。
酪農経営は飼料価格の高止まりにより厳しい状況におかれています。そのため、稲発酵粗飼料(稲WCS)など自給粗飼料の活用による飼料費の低減対策が取り組まれています。

品質の確認と成分分析用サンプルを採取する様子

稲WCSの採食状況を確認する様子
普及センターでは、収穫された稲WCSが有効に活用されるよう、品質の確認や給与についてアドバイスしています。
2025年3月
水落 栄一
▼稲発酵粗飼料(稲ホールクロップサイレージ)について
稲発酵粗飼料(稲WCS)とは、稲の実が完熟する前に、実と茎葉を一体的に収穫し、乳酸発酵させた飼料のこと。稲ホールクロップ・サイレージとも呼ばれます。水田の有効活用と飼料自給率の向上に資する飼料作物として、作付面積が拡大しています。(農林水産省ホームページより抜粋)